こんにちは!
本日はインターナショナルスクールで使われる“It’s like comparing apples to oranges”という英語表現をご紹介します。
目次
1. “It’s like comparing apples to oranges”という英語表現
“It’s like comparing apples to oranges”という英語表現は、日常の英会話でも時折使われる表現なので、一度は聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
直訳すると、「まるで林檎とオレンジを比較しているようだ」ですが、本当の意味は「全く比較しようがないくらい異なる」や「異質の違うものを比較しても無意味だ」ということを指します。
“It’s like comparing apples to oranges”の英語表現だけを聞くと、最初は同じ木の枝になる果物というジャンルなので、類似したものを比較しているかのようにも聞こえなくはないかもしれませんが、実はその真逆の意味で、「林檎とオレンジは全く違うものだから、比較しても仕方がない」ということを意図します。
この“It’s like comparing apples to oranges”という英語の表現の起源は定かではないのですが、古典文学では、「林檎とオイスター」が比較されている文章は残っているそうです。シェークスピアも、”As much as an apple doth an oyster, and all one.“というように「林檎とオイスター」を比べて文章をつづっていました。そこからより庶民的な食べ物の「林檎とオレンジ」に派生した可能性もあります。又、他のフランスやイタリアやスペインなどのヨーロッパ諸国では、“apples to pears”というように、「林檎と洋ナシ」を比較する場合があるそうです。いずれにしても、五感でも捉えやすい食べ物を引用し、「この二つの物は全く違う性質を持つから、比較しても無意味だ」という意味で使われているのは共通しているようです。
2. インターナショナルスクールのプリスクールやキンダーガーデンで“It’s like comparing apples to oranges”を使う場合
インターナショナルスクールのプリスクールやキンダーガーデンでも、“It’s like comparing apples to oranges”を使う場合はあります。特に、「兄弟や友達同士は違っていて当たり前だがら、同じように比較してはいけない」と指摘したい時に使われます。
例えば、インターナショナルスクールのプリスクールやキンダーガーデンの先生に、母親が「兄と弟に同じことを教えても、兄の方はすぐに覚えてできたのに、弟は全く興味をも示してくれないんです」と相談しても、この“It’s like comparing apples to oranges”という答えがかえってくるかもしれません。例えば、次のような英会話になります。

It’s just like comparing apples to oranges. They’re two separate individuals and they have a mind of their own. You can’t expect them to react the same to the same thing.
(それは違って当たり前ですよ。二人は個性の異なる個人であって、それぞれの考え方があります。同じ事柄を教えたからといって、同じ反応を期待してはいけないでしょう。)
余談ですが、日本のカルチャーとしては、かつては統一した教育の元に同じような人間を育てるのが望ましいとされてきましたが、アメリカなどではindividualismという個人の権利と自由を尊重する個人主義が重んじられてきたので、たとえ兄弟であっても、母親や父親ですら、子供を比較するのをタブーとする風潮があります。同じ一卵性双生児でも、違うのが普通なので、ましてや年が離れた兄弟や姉妹なら尚更違って当たり前という発想です。
このように、同じ親の元から生まれた兄弟を比較する時や、友達同士で発達スピードが異なることで悩んでいる場合に、“It’s like comparing apples to oranges”という表現を使い、「違う個人を比較しても、違って当然だから」という意味合いでインターナショナルスクールのプリスクールやキンダーガーデンではママ友同士でも活用されるフレーズです。
それぞれの個性を尊重し、違いを認め合う事がインターナショナルスクールでは大切にされていると思います。
3. まとめ
”It’s like comparing apples to oranges”というような慣用句は英語でidiomと呼ばれ、より多くのidiomを覚えることにより、一段上の英会話ができるようになると感じます。
機会があったら、活用してみて下さい。









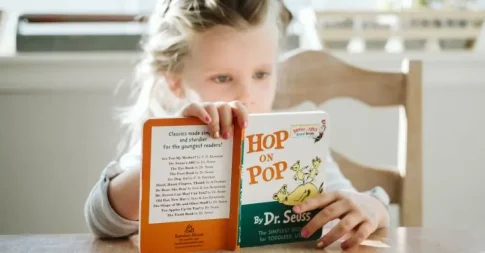








I tried to teach the same thing in the same way for his older brother and also to the younger brother. But even though his older brother learned it really quickly, the younger brother doesn’t even show any interest in it.
(兄と弟に同じことを教えても、兄の方はすぐに覚えてできたのに、弟は全く興味をも示してくれないんです)