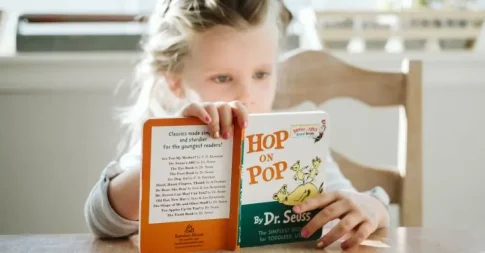このページでは、保育士資格を持ち、日本にある米軍基地内の保育園で勤務経験のあるインターママ英会話の講師が、米軍基地内の保育園の1日の中の保育スケジュール、内容や、魅力、そして日本人目線での印象等についてご紹介します。
米軍基地内の保育園や学校にお子様を入園(入学)させるには諸条件があるものの、興味をお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今回こちらでご紹介させていただきます。
目次
1. 自己紹介
私は日本の保育士資格を保有しており、TOEICは975点、英検は1級を取得しております。
日本の認可保育園で勤務している時に、基地内の保育園で働くという選択肢があることを初めて知りました。
キッカケは、当時、一時保育サービスを利用しに来ていた基地関係者の子どもたちがいたことでした。軍関係者の中には、日本に滞在している間、子どもたちを積極的に日本文化に触れさせたいと考える人もいます。そういった保護者が園に見学に来たり、一時利用したりする際の英語対応を行っているうちに親しくなり、ある時、軍関係者の保護者の方から、基地の保育園で働いてみては?と勧められました。
当時は、私のような一般人が基地の保育園で働けるとは知らず、とても驚きましたが、日本人の先生たちもいると教えてもらいました。その後、採用窓口を調べ、履歴書を提出してみると、ちょうど産休に入る先生の臨時のポジションが空くタイミングでした。
アメリカと日本では、保育に必要な資格が異なるため(アメリカ資格はCDA/Child Development Associate)、必ずしも保育士免許が必要なわけではありませんでしたが、それまでの保育経験から、無事採用に至りました。
その後は運良く欠員の出た常勤のポジションにトランスファーすることができ、それから約10年にわたり、0歳児から時には10歳の学童まで、様々な年齢の子どもたちを担当しました。
2. 日本人家庭など、英語があまり得意でない子供に対しての保育園側の対応
私が働いていた保育園では、だいたいどのクラスにも1割くらい日本人とのハーフの子どもたちがいました。お父さんが米軍関係者、お母さんが日本人という家庭です。
子どもたちは年齢が小さければ小さいほど、お母さんと一緒に過ごす時間が長いため、日本語が先行しているパターンが多いです。そのため、最初は日本語を話す先生たちによく懐きます。しかし園での生活に慣れてくると、言葉を超えたコミュニケーションで子ども同士は打ち解け、関わりの中で徐々に英語が増えていきます。自己主張が強めなアメリカ人の子どもたちの中にいると、一種のサバイバル意識が目覚めるのか、ストレートな意思表示が増えてきます。
私が働いていた園では、0歳の頃からAmerican Sign Languageを教えていました。まだ言葉らしい言葉を発する前の段階から、遊びや食事の場面で、eat、drink、more、all done、please、Thank you など、よく使うサインから教えていきます。これは週ごとのレッスンプランに組み込まれていて、徐々にバリエーションを増やしていきます。子どもたち自身は、これが英語だと認識しているわけではなく、このサインをすればオヤツのお代わりがもらえる、好きな本を読んでもらえるという具合に、自分にとって必要なサインを体験から覚え、成長と共に徐々に言葉に移行します。それからは子ども同士、楽しい感情を共有したり、怒りの感情をぶつけ合ったり、心が強く動く時に、新しい言葉や表現をどんどん吸収していきます。
友達とのケンカの場面では、日本の保育園でも同じですが、うまく言葉が出ないせいで、代わりに手が出てしまうこともよくあります。そういう時は、1対1で静かに対話する時間を取りました。He did it! と相手を責める言葉が先に出ることが多いのですが、自分はどう思ったのか?相手にどうして欲しかったのか?という気持ちを引き出し、それじゃあ、こう言いたかったの?と何パターンか英語で言ってあげると、その中の表現を拾って相手に伝えます。
I don’t like it! ときっぱり相手に言えるようになると、関わり方や距離感を探り合い、友達同士のトラブルも自分たちで解決できることが増えます。子どもなりに、対等に渡り合っているという感覚は自信に繋がるようで、英語習得のスピードが一気に加速します。
3. 園児の人種比率
保育園には様々な人種の子どもたちが通っています。
基本的に、基地で暮らす人たちは、軍人とその家族か、働きに来ている一般人です。私が勤めていた保育園の園児の人種比率は、白人>アフリカンアメリカン系>ヒスパニック系>アジア系(フィリピン、日本、韓国)の順で多かったと思います。そのため、英語以外にもさまざまな言語が飛び交い、日本人家庭の子どもに限らず、英語が得意ではない子どもたちは多くいます。そんな中でも、みんなとコミュニケーションが取れる共通言語を徐々に認識し、次第に通じる言葉を選ぶようになっていきます。
4. 米軍基地内の先生について
基地内の先生達の8割方は軍人の配偶者や家族なので、以前はどの国のどの基地にいた、夫はどのユニット所属、と自己紹介するのがお決まりのパターンでした。
特殊な環境なので、先生たちの人種ももちろんバラバラです。米軍は世界中に基地があるため、世界各地で新たな家族が生まれ、家族で世界中を飛び回っているイメージです。そのため、軍人の配偶者や家族である先生達も、限られた貴重な数年間を同じ基地に居合わせたお仲間と共にするといった感覚ではないでしょうか。日本人従業員の枠は、地域、または園によって異なると思いますが、私がいた保育園では全体の2割程度だったと思います。
最初の章でも触れたように、アメリカと日本では資格が異なるため、基地の保育園では資格が必須ではありません。ただ、それまでに積み重ねてきた知識や経験は考慮されます。私が働いていた保育園では、保育士免許や幼稚園教諭の資格を持っている先生が多くいました。
採用されてすぐは保育補助として仕事を覚えながら、各自が幼児教育に関するテキストに沿って英語で学習を進め、毎月レポートを提出する形で単位を積み重ねていきます。各園に常駐しているトレーナーから直接指導やフィードバックを受けて、1年半ですべての単位を取得すると、昇進の機会が与えられ、担任としてクラス運営全般を任されるようになります。アメリカ赤十字のCPR(心肺蘇生法)やファーストエイドなどの講習も定期的に受講し、万が一の時に対応出来るよう、常にアップデートも行っていました。
5. 1日の中の保育スケジュール、内容
若い軍人たちの1日は、早朝のマラソンからスタートします。そのため、まだ暗いうちから、早番の先生たちが子どもたちを受け入れます。そしてだいたい7時の朝食時間の頃に全員が登園して来ます。
朝食を済ませると、レッスンプランに沿って、アクティビティがスタートします。大きな筋肉を使う運動系のアクティビティ、指先などの細かな筋肉をあやつるアート、頭を使うマス&サイエンス、リズム感を養うミュージック、絵本などを用いた言語系のアクティビティなどがレッスンプランに組み込まれており、子どもたちの習熟度を観察・記録します。天候が許せば園庭で自由遊びもしますし、夏は水遊びもします。
0歳児の食事風景は、手掴みで自由に食べる練習をさせるため、あまりの散らかり具合に最初は驚きました。もちろん日本の保育園でも掴んで食べる練習はさせていましたが、キレイに残さず食べるという日本の保育園とはだいぶ違いました。年齢が大きくなってくると、欲しい物を欲しい分だけよそって食べるビュッフェスタイルでした。
昼食を食べた後は、歯磨きとトイレを済ませ、絵本を読んでお昼寝をします。昼寝から目覚めると、オヤツを食べて、お迎えの時間まで自由遊びをします。レッスンプランには、アメリカ以外の文化のアクティビティも多く取り入れられていて、アートなどの制作物は教室内にしばらく展示した後、各自持ち帰ります。折り紙や書道など、日本文化を取り入れたアクティビティは保護者からいつも好評でした。
6. 年間のイベント事
年間のイベント事は、基本的にはアメリカの祝祭日に沿っていますが、4月のThe Month of the Military Childが一番大きなイベント週間でした。
スポーツデーは、お気に入りのフットボールチームや野球チームのユニフォームで登園し、各年齢に合ったスポーツアクティビティで盛り上がりました。奇抜な髪型を競うクレイジーヘアデーは、ヘビメタのように髪を逆立てたり、カラースプレーで派手に色を付けたり、息子の頭を刈って名前の頭文字を浮き上がらせたりと、お父さんたちが特に張り切っていたのを思い出します。
チグハグな服装のミックス&マッチデーは、上下左右バラバラの服や靴で誰よりも目立とうとみんな気合いを入れて登園し、教室が大爆笑に包まれました。ストーリーデーは、絵本や物語のキャラクターになりきって1日を過ごし、廊下をパレードしました。
学童を担当していた時は、度々タレントショーが開催され、女の子たちは振り付けを考えて流行りの曲を披露し、男の子たちはヒップホップダンスやラップバトルを繰り広げ、生まれ持ったリズム感の違いにカルチャーショックを受けました。夏休みのある日は、パジャマで登園して、一日中映画を見てゴロゴロ過ごすムービーデーなんて日もありました。日本では苦情が殺到しそうですが、楽しむ時はトコトン楽しむ姿勢がアメリカらしいなあと思いました。
一方で、お父さんやお母さんが急な任務で長期間いないこともよくあります。特殊な環境ですから、複雑な事情を抱える家庭や、ストレスレベルの高い子どもたちもいます。そのため、準備せずとも手軽に楽しめるイベントが多かったように思います。日本の保育園のお遊戯会や運動会は、何ヶ月も前からたくさん準備を重ね、子どもたちはもちろん、保護者も保育士も大変な時間と労力を注ぐので、この点は大きな違いでした。
7. 保護者と先生とのコミュニケーション
毎朝毎晩、受け入れとお迎えの時には、必ず保護者と会話をします。
昨日からちょっと風邪気味だとか、しばらく任務でパパがいないなど、個々の事情を把握する貴重な時間なので、こちらにもそれなりの英語力とコミュニケーション能力が必要でした。この先生は英語があまり分からないという印象を持たれてしまうと、後々自分が仕事しづらくなるため、当時は必死で勉強していました。また年長さんの担当になった時などは、絵本の読み聞かせで発音が違うと、子どもたちはかなりシビアに指摘してくるので、先生としてのメンツを保つためにフォニックスも練習しました。
ちなみに、基地の保育園は、教室内での先生と子どもたちの人数比を常に記録しているログがあり、部屋からひとりでも出入りする際は必ずサインインorサインアウトし、保護者もその都度サインする決まりとなっています。
米軍基地は人種のるつぼなので、個々の常識や要望が大きく異なると感じることはよくありました。例えば、日本の保育園の場合、多少の個人差があるとはいえ、大多数が共通認識の基で動いている感覚がありますが、基地の保育園では、そもそも育った国も言語も違い、文化や宗教も異なるため、常に要望を書面で確認するということがありました。クリスマスやハロウィンのような宗教的背景のあるイベントは、多方面に配慮し、露骨な表現は控えて皆が楽しめるホリデーという形で行いました。こういったイベントへの参加の有無、園生活における写真撮影の可否というような確認事項を、事前にすべての保護者に対して行っていました。各家庭の要望を把握し、それぞれ対応するのは大変でしたが、皆が当たり前に異なっているという認識で、ルール違反でない限りは尊重します。
8. 保護者同士のコミュニケーション
軍は完全な階級社会の環境なので、保護者同士の関わりも少し特殊でした。子ども同士は仲良しでも、お父さんたちは、片や地位の高いオフィサー、片や新米軍人なんてこともよくありました。そういったお父さんたちのお迎えの時間が被ると、新米パパが背筋を伸ばして敬礼している姿もよく見られました。
お母さんたちは、基地内で先生として働いている人や、事務職、エッセンシャルワーカーなど様々でしたが、共通点を見つけてコミュニケーションを取るのが上手だと常々思っていました。
園では、保護者をバーベキューやランチに招待したり、お迎えの時にアイスクリームを一緒に食べるイベントなどもあり、一緒にテーブルを囲む機会はよくありました。また、子どもたちの誕生日には、保護者がケーキを持参してクラスみんなでお祝いしました。アレルギーなどの観点から手作りはNG。持ち込めるのは基地内で売られている特定のケーキに限定されているのですが、そのカラフルなデコレーションに、みんな舌が真っ赤になり、強い甘さでシュガーハイになる子どもたちが続出しました。
9. 保護者面談の内容
基地の保育園では、半年に1回のペースでカンファレンス(保護者面談)があります。
0歳児から各家庭と面談をし、園での様子や、発達段階の確認、今後の成長に向けた取り組みなどを話し合います。世界中の米軍基地で共通の発達段階のブックレットがあり、それに沿って、個々の成長を記録していきます。例えば、0歳なら目で人や物を追う、首を上げる、寝返りをする、手や指先で物を掴む、というようなひとつひとつの発達段階がグラフで可視化されており、保護者の要望なども取り入れながら、その後のレッスンプランにアクティビティとして組み込み、さらに半年後にまた面談で振り返るといった感じです。
10. 厳しい基準に基づいた管理体制
米軍では、3年ほどのスパンで転勤があるため、軍人の家族たちはみな頻繁に国をまたいで引っ越すことになります。そのため、どこの基地に行っても一定の保育が受けられるよう、環境面や安全面、カリキュラムなどはすべて厳しい基準に基づき管理されています。
また、部屋の四隅には監視カメラが設置されており、事故やケガがあった際の安全面の検証や責任の所在を明らかにする厳しさもありました。常に監視されている窮屈さがあり、すべてにおいてルールに縛られる環境でしたが、アメリカは訴訟の国ということもあり、映像のおかげで先生たちの立場が守られたこともありました。
11. 米軍基地内保育園に子供を入れる事を検討されている保護者の方向けのメッセージ
幼い頃から、さまざまな人種や文化、言語に触れさせてあげることは、とても貴重な体験になると思います。人と違うことが珍しく見える日本とは異なり、基地の中では誰もが当たり前に違っています。これは頭で理解しようとしても難しい、感覚的なものです。外国にルーツを持つ子供が多いインターナショナルスクールでもこの点は同じだと思います。
また、私たち日本人の大人の多くが中学校から習っていた読み書き先行の英語と、幼いうちからコミュニケーションのツールとして使う英語は、学びのプロセスが大きく異なります。英語を学び続けるひとりの学習者としても、その過程を目の当たりにする体験は大きな財産となりました。
私がいた米軍基地内の保育園では、地元の保育園児たちとの文化交流会などもありました。興味のある方は、地域の情報を調べて参加してみるのも良いかも知れません。